年間を通して日照時間が長く、雨の日も少ない晴れの国・岡山。日本一の生産量を誇るマスカットやピオーネ、清水白桃や愛宕梨などは、岡山県を代表する特産品として知られている。果実のほかにも近年、注目を集めている野菜がある。その一つが、黄ニラだ。高級食材として一部地域で流通している黄ニラの機能性が、岡山県の産学官研究で明らかになりつつある。
緑黄色野菜の一つであるニラはネギ属の多年草。流通しているニラ(青ニラ)は一般的に緑色で葉が食べられているのに対し、黄色が鮮やかな黄ニラは、上下を切った中間部が食される。黄ニラは青ニラと同じ品種だが、養分を蓄える栽培法によってブランド力を高めてきた。
具体的には、青ニラの地上部を刈り取り、黒いビニールシートで根を覆って太陽光を遮断する「軟化栽培」という方法で育てられたものが黄ニラだ。栽培期間中に1~3時間程度太陽光を浴びせ、出荷直前に天日干しした後、黄色が濃くなった中間部のみが出荷されている。

青ニラには独特の刺激があるが、黄ニラはにおいがない。甘くマイルドな味でやわらかく、青ニラよりもうま味成分が多いこともわかっている。サラダやおひたし、みそ汁や卵とじなどが定番の用途だ。
「岡山県は黄ニラの国内生産量のシェア7割を占めている。地域農産物などの高付加価値化を推進している岡山県農林水産総合センターから依頼を受け、2016年に研究をスタートさせた」と話すのは、就実大学薬学部の川上賀代子助教(生化学研究室)だ。
共同研究(「岡山県外部知見活用型・産学官連携研究事業」)では、”抗酸化作用”という切り口で黄ニラの高付加価値化の可能性を検証することになった。「酸化ストレスは糖尿病や動脈硬化など、多くの生活習慣病にかかわっている。黄ニラの機能性に関する論文は出ていなかったため最初は手探りだったが、食品由来の抗酸化物質として知られるポリフェノール、生体内で産生される抗酸化物質のグルタチオン上昇活性などを解析していった」と、川上助教は当時のようすを振り返る。
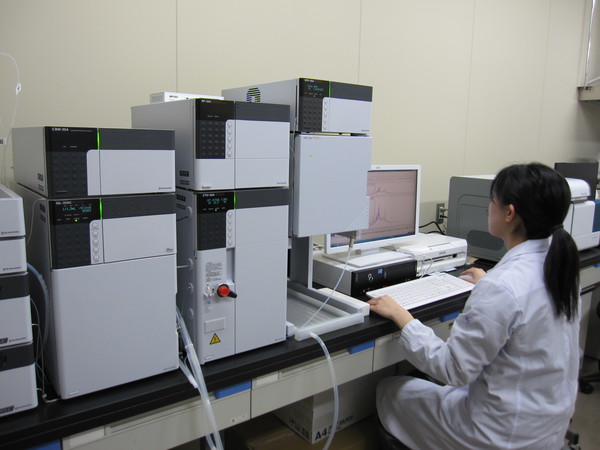
岡山県農林水産総合センター農業研究所で栽培されている「黄ニラ」「岡山いちご」「おいCベリー」「さがのほのか」「シャインマスカット」「オーロラブラック」「桃太郎トマト」「清水白桃」の岡山県産農産物8点を川上助教がスクリーニングした結果、黄ニラはオーロラブラック(皮あり・エタノール抽出)に次いで総ポリフェノール量が多いことがわかった。
また、ヒト肝臓由来の細胞にそれぞれのエキスを添加してグルタチオン上昇活性を調べる試験では、黄ニラ、シャインマスカット、清水白桃によって細胞内グルタチオンが有意に上昇することが明らかになった。
川上助教によると、「黄ニラによる活性は特に顕著で、比較対象であるエキス添加なしの通常の細胞に比べて1.7倍のグルタチオン上昇が認められた。スーパーオキシドアニオンラジカルという活性酸素の消去活性も、8つの農産物の中で黄ニラが最も高かった。くわしく調べてみると、黄ニラにはグルタチオン以上の活性酸素消去能があることがわかった」とのことだ。
2017年の研究では、抗酸化作用の季節変動なども検証された。その結果、5月に収穫された黄ニラの活性酸素消去活性が最も強く、冬季にかけて活性は低くなる傾向が認められた一方、総ポリフェノール量は8月が最も低く、10月が最も高くなるという結果が得られたそうだ。
「黄ニラには抗酸化作用のあるアスコルビン酸も含まれている。含有量は夏季が少なく、冬季に増えるという報告がある。抗酸化作用に寄与しているのは、ポリフェノールやアスコルビン酸の以外の未知の成分の可能性もある」と話す川上助教。今後のさらなる研究にも注目が集まる。
有効成分の特定を含めた機能性の検証のほか、金色に輝く黄ニラの流通網の拡大も期待されている。「健康にいいということがわかってきたので、研究成果を皆さんに還元していきたい。黄ニラは岡山県のスーパーで販売されているが、県外では東京の高級料亭など一部でしか見ることはない。まずは黄ニラを知るきっかけになれば」と、川上助教は最後に明るく話してくれた。
