山形県立米沢栄養大学の加藤守匡教授(健康栄養学科)は、食用菊「モッテノホカ」に含まれる“ルテオリン”の抗うつ作用を2018年11月に発表した。将来的には、脳神経細胞を保護し、脳機能を高める食品の開発を視野に入れている。
山形県は食用菊の生産量日本一。主に刺身の添え物として流通しているものの、食用菊を食べるのは全国的に見ると少数派ではないだろうか。一方、山形県には古くから菊を食する文化があり、天ぷら・酢の物・おひたしなど、旬の10月下旬には食用菊が食卓を彩る主役の一つとなる。

食用菊の中でも、特に味と香りに定評があるのが「モッテノホカ」というブランドだ。米沢栄養大学のある置賜地方は、モッテノホカの県内生産量の6割を占めている。加藤教授の研究は、地域振興の期待も受けてスタートした。
山形県民にとって身近な食材として愛されているモッテノホカについては、これまでにも抗酸化作用・脂質代謝改善作用・抗ピロリ菌活性作用に着目した研究が米沢女子短期大学などで推進されてきた。多岐にわたる機能性を有するモッテノホカだが、加藤教授が注目しているのは脳神経細胞の保護効果だ。これまでの研究で、モッテノホカが、うつ病や認知機能低下の予防・改善に役立つ可能性が示唆されているという。
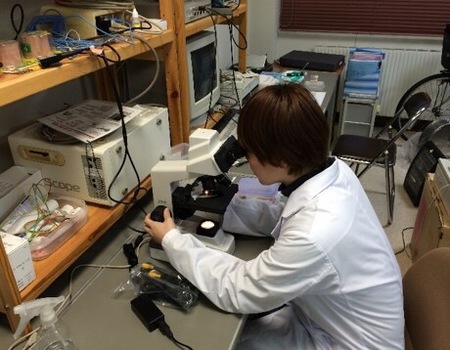
「培養細胞を用いた実験では、モッテノホカに含まれる“ルテオリン”による神経軸索の伸張が示唆された。軸索は情報の出力には欠かせないもので、認知機能についての知見を活かせる食材だと感じた」と、加藤教授は振り返る。ルテオリンは代表的なフラボノイドの一つで、伝統薬に用いられてきた多くの植物に含まれている機能性成分だ。
国内外の研究で、ルテオリンの中枢作用への影響が検討されている。国内における研究は発展途上だが、加藤教授はルテオリンの抗うつ・抗不安作用を掘り下げている。「モッテノホカは多量に食べる食材ではない。ルテオリン単独の効果では実用化が難しいと思い、研究分野である運動とのシナジーを模索してきた」と、食と運動の相乗効果に期待している。医学博士として運動による認知機能改善について研究してきた背景をベースとした切り口の研究といえる。
健常マウスをストレス環境下で飼育する実験では、ルテオリンと低強度のトレッドミル運動を組み合わせた相乗効果が評価された。試験期間中、私たちが日常生活で食べる量を想定して、ルテオリンはマウスのエサに混ぜて与えられた。「高濃度の溶液を投与するわけではないので、ストレスを与えながらもマウスには確実にエサを食べてもらう必要があった。適切な運動の選択にも思考錯誤を要した」と加藤教授は研究の苦労を語る。

3週間後、ルテオリンと運動を組み合わせることによってマウスの視床下部領域のストレス反応は減弱することが明らかになった。ストレスに伴って増えるc-Fosたんぱく陽性細胞数が減少していたのだ。この結果について加藤教授は、「ルテオリンには神経軸索をストレスから保護する作用があるのかもしれない。運動によって細胞の感受性が高まり、そこにルテオリンが合致している可能性も十分に考えられる」と分析している。機能性食品だけに頼るのではなく、運動など私たち自身の努力も必要ということだろう。
「モッテノホカに抗うつ作用があるといっても、薬のように劇的な効果があるわけではない。日常的な摂取で効果の高まる方策を模索している。うつ病のモデルマウスではなく健常マウスを実験に用いたのも、そのためだ」と話すとおり、加藤教授が目指しているのは研究成果の実用化だ。今後の展開として、うつ病の予防・改善に効果的な摂取量や摂取期間を明らかにするヒト試験が計画されているそうだ。

「山形県ではスーパーでも食用菊が食材として陳列されている。これは独自の文化といえる。モッテノホカの研究がさらに進み、脳神経細胞の保護を促す高い機能性をもった食品の誕生につながれば、ニッチだった食用菊文化の拡大のきっかけになるのではないか」と加藤教授は話している。
高齢化社会やストレス社会と脳機能は密接な関係にある。食卓を彩るモッテノホカが、日本の将来を明るく灯す切り札となるかもしれない。今後のヒト試験や作用機序の解明など、加藤教授の研究には大きな期待がかかっている。
