日本海側で古くから郷土伝統食として親しまれてきたエゴノリに、血糖上昇抑制作用と脂肪肝抑制作用があることがわかってきた。福井県立大学生物資源学部の村上茂教授と輪島・海美味工房(石川県輪島市)による共同研究の成果。ヒトで作用を確認し、”健康食材”としてエゴノリの新たな魅力を発信していく。
日本海沿岸に多く分布しているエゴノリは、エゴ草やイゴノリとも呼ばれるイギス科エゴノリ属の紅藻。コンブなど大きな海藻に着生して成長していく。石川県輪島市はエゴノリの産地の一つだ。2018年3月、「輪島の海女漁の技術」が重要無形民俗文化財として登録されたのは記憶に新しい。アワビやサザエをはじめ、ナマコ、イワガキ、カジメ、イワノリ、ワカメ、テングサ、 イシモズクなどとともに、エゴノリも素潜りによる伝統的な漁撈により水揚げされてきた。

エゴノリに目をつけたのは、「国際タウリン研究会」の理事長を務める福井県立大学の村上茂教授だ。村上教授は、魚や貝、イカやタコなどに含まれるアミノ酸誘導体の一つである「タウリン」の機能性について長年研究してきた。低下した心臓や肝臓の働きを回復させるなど、タウリンは体の機能を正常に保つための重要な働きを持つとされている。
「栄養ドリンクなどに入っているのは化学合成されたタウリンだ。食材に含まれる天然のタウリンを活用したいという思いがあり、研究を続けてきた」と村上教授。魚介類はタウリンを多く含むものの、機能性食品としての製品化は簡単ではないため、海藻を研究対象とするようになったそうだ。

海藻は低カロリーである上、ビタミン、ミネラル、食物繊維など栄養素やさまざまな活性成分を豊富に含んでいるが、タウリンの含有量に関する詳細な解析データはなかった。
若狭湾で採取した約50種類の海藻を対象に、村上教授がタウリンの含有量を調べた結果、海藻により大きなバラつきがあるが、エゴノリにもタウリンが含まれることを発見した。2015年のことだ。
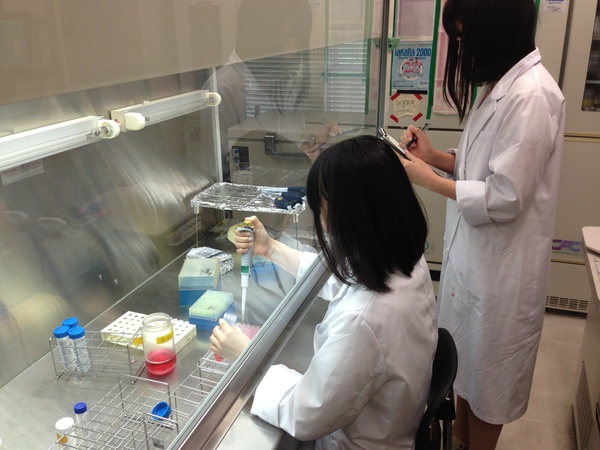
村上教授が実験用のマウスを用いて実施した動物実験では、エゴノリエキスをあらかじめ投与しておくと、炭水化物を与えた後の血糖値の上昇が抑制されることがわかった。また、ヒト由来の肝細胞株を用いた実験では、脂肪の蓄積を抑制する働きが見出されている。研究の成果は、2018年3月に発表された。
「エゴノリに含まれる多糖類によって食後血糖値の上昇が緩やかになれば、動脈硬化の原因となる血管へのダメージが抑えられる。タウリンが肝臓に保護的に働くほか、腸内環境の改善による免疫力アップも期待できる」と村上教授は解説する。現在、肥満や糖尿病のモデルマウスを用いた動物実験の準備が進められているそうだ。ヒトで作用を確認し、エゴノリを使用した機能性食品の開発を目指していく。

エゴようかん 。テングサ、オゴノリと同じく、エゴノリはところてんや寒天の材料になる
煮出して固めたゼリー状の「えご」「おきゅうと」など、郷土伝統食として親しまれてきたエゴノリ。近年、家庭で作られる機会が少なくなり消費量も減少しているが、北陸発・健康食材の新定番として新たなファンを獲得できるかもしれない。
なお、新潟県長岡市には「越後えご保存会」があり、越後の郷土伝統食である「えご」を世に広め、子どもたちに継承していくため、さまざまな取り組みが行われている。
